

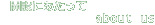
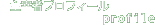

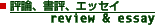

|
 |

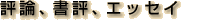
【食の工業化・グローバル化をめぐって】
●食することの自由
BSEが日本でも確認されて以来、飽食から粗食への回帰を主張する議論や、いささか情緒的な肉食回避論があちこちで展開されている。
日本の食から肉食が排除されているのは、タンパク質を魚や豆類で十分に摂取できる環境があったからだとされ、そのバランスのよい摂取が日本人の食の特徴であったとも主張される。では、日本人には肉食は不要なタンパク源だったのだろうか。日本人は肉をまったく食してこなかったわけではない。森林の多いこにの列島にはシカやイノシシなど多くの動物が棲息していたから、これらの動物が重要なタンパク源であったことは十分に想像できる。縄文人は狩猟民であったし、弥生人も銅鐸の図柄にも見られるように狩猟に従事していた。わたしたちの遺伝子にも肉食への渇望が確実に刻み込まれていることは明らかである。
それなのに、肉食が日本人の食習慣から排除され、粗食を伝統とする発想が支配的になったのはなぜだろうか。この国の食文化の不幸は、肉食を禁じられたところに始まる。稲作を神聖視し、その対極として肉食を禁じたところにはじまる。日本人、とりわけ庶民は豊かな食材を前にしながら「食することの」自由を奪われた歴史上まれな人間集団であった。そのような支配の下で、日本人はほんとうに米と野菜と魚による食に甘んじていたのだろうか。そうではなかったろう。さらに言えば、アイヌや沖縄の伝統食はいったいどのように評価すべきなのだろうか。粗食を日本固有の文化とする人たちの主張はあまりに狭い。
明治の近代化以降、肉食に対する制限も制約もなくなったかに見えるが、実際には権力的な強制から市場原理による強制に取って替わられたにすぎない。例えば、クジラを食することは、わたしの世代にとっては貧しい人びとに市場によって強制された肉食であった。捕鯨船団による南氷洋捕鯨は安価な肉製品の「生産」そのものであった。それは食の工業化とグローバル化の先駆けであったともいえよう。
現在、世界中の食材を安い価格で食せるという見せかけの自由の享受の背後で、高い輸入依存度と工業化率が複合した最もリスクの大きい食が強制されている。BSE問題はまさにそのリスクを端的に示している。
食することの自由、安全なものを自ら選び取れる自由を手にするためには、学ぶことから始めなければなならない。
(ニコライ・ヴィルム著、花房恵子訳『肉がよくないなんて、誰が言った』家の光協会、2002年8月、「監訳者あとがき」より抜粋)
●「食」の工業化とグローバル化がもたらすもの
いま、「食」のあり方とその安全性をめぐる不安が世界中で急速に広がっている。遺伝子組み換え食品、環境ホルモンが人類や生物に与える影響、記憶に新しい大阪府堺市を中心にした大腸菌O157中毒の大量発生や雪印乳業大阪工場の食中毒事件のような大規模で広域的な事件は言うに及ばず、食中毒の発生は季節を問わず日常化している。国外に目を転じると、ヨーロッパを中心に狂牛病や口蹄疫が蔓延し、畜産業が深刻な経営危機に追い込まれているだけでなく、肉食というヨーロッパ食文化の根幹そのものが揺らいでいる。過食と偏食の傾向が強まる中で健康食品への依存が増えている。人間の基本的営みである「食」から「自然」が急速に奪い去られつつある。
大規模な事件が起きるたびにヒステリックな汚染源と責任者探しが展開され、消費者はそれにあおられてパニックに陥っている。たいていはこの探索は失敗するか、責任者の処罰もなく終わる。食しているものが本当に安全なのか、この不安とリスクの原因は何なのか、その答えはいつも明快に示されないままである。
不安の背景にあるものは明らかである。食料が自然と直結した「農産物」であることをやめて、「工業製品」と同じように工場で製造され供給される仕組みに、私たちの生活がはめこまれてしまったことだ。食料の生産と供給も以前は都市の周辺の農漁村との安定的な循環の上に打ち立てられていた。いまでは世界じゅう至る所で農産物が生産され、加工され、輸入される。食料のグローバル化が進んでいるのだ。消費者には生産と流通の仕組みが見えなくなり、どこで生産されたのか、どのような土壌でどのような農薬を使ったのか、ほとんど知らされることはない。汚染源や責任者など、消費者にはわかるはずもない、知らされているのは、スーパーやコンビニでいつでも安く手にはいり、手軽に食せると言うことだけだ。私たちは確かに「食」の工業化とグローバル化によって低価格と利便性を手にできた。しかし、まさにそのことによって、これまでに体験したことのない生活と生命に対するリスクに直面しているのである。
21世紀を迎え、地球環境危機の克服に真摯にとり組むことが急務となっている。そのためには、どうしてもモノの作り方だけでなく、生活そのものも革命的見直しが必要になる。この世紀はあらあゆる生活要素のインプットを、環境に負荷を与えないか、本当に生活の質を向上させるものかを基準に判断する時代になる。もはや経済的効率と価格だけが基準の時代ではないのだ。この時代の最重要課題である「食」の危機の克服のためには、生活を市場原理にまかせっぱなしの受動的なもから、安全なもの、質の向上に資するものを再び選び取る主体的生活態度を取り戻さねばならない。また、かってのような地域に根ざした生活様式を作り出さねばならない。「食」を市場原理の支配から解放し、地のもの、旬のものを食すること、工場製食品の使用を減らして素材から自分で調理する生活態度と時間のゆとりを取り戻すこと、そこに環境の時代に生きる豊かさの核心がある。
(ハンス・ウルリッヒ・グリム著、花房恵子訳『悪魔の鍋ー「食」のグローバル化が世界を脅かすー』家の光協会、2001年7月、「監訳者まえがき」から抜粋)
●合成ビタミン、サプリメントの流行が意味するもの
グリムさんの仕事が日本に紹介されるのは、『悪魔の鍋』(家の光協会、2001年7月)に続いてこれが2冊目である。工場製食品がもたらす食と健康の危機を解明した前作に続いて、本書では工場製ビタミンを対象にし、その過剰摂取がもたらす害を鋭く暴き出している。そこに紹介されている食の風景と合成ビタミンの普及の状況は、そっくりそのまま日本にも当てはまる。それどころか、日本ほど食にかかわるリスクが日毎に深刻になっている国はないのではないかとさえ、考えさせられる。
かってこの国の食文化は豊かで健康でバランスのとれた食事、あますところなく調理し、食する態度によって世界に知られ、日本食は世界の模範とされてきた。沖縄の食にいたっては、世界最高の長寿食として注目を浴びている。この国の食材が海外に大きく依存するようになっても、この評価が維持されていたのは、日本人の食材を見抜く力と、バランスのよい組み合わせを作り出せるセンスのおかげであった。その食文化がいま、急速に崩れはじめている。
食が自然と直結したものではなくなり、食材が工場生産され供給される「食の工業化」の流れに、私たちの食生活はまるごと飲み込まれはじめている。工場製食材が家庭料理になかで主流を占め、外食の比重も急速に高まっている。「食のグローバル化」も急速に進んでいる。周辺諸国の低賃金労働力を利用して海外で食材加工が進み、魚の切り身からホウレンソウのおひたし、大根おろしに至るまで日常の食卓を飾っている。このような現実に対応して食材製造や輸入に携わる企業の倫理感は低下し、不正表示は日常化している。伝統的食文化からと切断されて味覚を失った若者が増えている。伝統食を忘れ、食の手抜きに精を出す家庭人が増えている。異質の食文化が生まれている。
飽食の時代といわれるが、それは美食とは到底言えない性質のものだ。質の悪い食品で胃の腑を満たし、食の廃棄物を増やす、食い散らかしの時代でしかない。まさに「食の貧困化」の時代としか表現しようがない。どのような内容の食材を食しているのか、それがどれほどの栄養価を持ち、どれほどまで安全なのか、誰にもわからない。だから、質の悪い飽食と歩調を合わせて、不安感が醸成され、「手作り」「無添加へ」への奇妙なまでの渇望が高まる。サプリメント、機能性食品が急速に普及するのも当然のことであろう。日本人の食は「食の工業化」「食のグローバル化」がもたらす「リスク連鎖」に確実に絡め取られつつあるのだ。
この国の現実を見るとき、合成されたものの過剰摂取を戒め、天然食材を可能な限り利用してバランスよく食すること、適度な労働と運動を勧める本書の主張に、私は大賛成である。ただ、日本の「食のリスク連鎖」に絡め取られいる度合いは、ヨーロッパよりもはるかに深刻である。日本の実情をふまえてさらに厳しい警告が発せられなければならないと思う。
21世紀には「食のリスク連鎖」が地球規模で拡大する世紀になることは避けられないだろう。この世紀には、地球人口の爆発的増加と都市への人口流入が進み、食糧供給能力との不均衡が拡大している。水や耕作に適した土地の不足も深刻になる。気候変動は農業や漁業にも深刻な影響を与える。地球環境保全の努力が格段に前進したとしても、増大する人口に十分な栄養を保障することは難しく、食の工業化とグローバル化は避けられない。天然食材への回帰を主張するだけでは、解決策にならないのは明らかである。課題は、そのような工業化の状況下で「生活の質」をどのように維持できるかである。この国はかって深刻な公害問題を体験したことによって、一転して公害防止策で世界をリードするようになったが、それと同じように、この国がおかれている深刻な状況への反省が強まれば、地球規模の「食のリスク連鎖」の解決で先駆的役割を果たすことも可能ではないだろうか。
そのためには、何よりもまず、日本の食が直面しているリスクを学習しなければならない。そして、実際に体験によってそれを確かめることが必要である。食材を原産地、栄養価、添加物の有無を自分で吟味して、手間暇かけて調理すれば、見てくれはよくなくても、それがどれほど美味であるかを体験できる。外食よりも家庭で栄養のあるおいしいものを食べられる。「地球の視野で考え、身近なところから行動しよう」、これは地球環境問題への対応策のありかたとしてよく引用されるスローガンである。食の危機への対応はまさにこの通りなのである。
私たちは、そのことによって食の危機だけでなく地球環境全体の保全にも貢献できる。レトルト食品1袋あたり、あるいはカロリー、ビタミンあたりの物質・エネルギー集約度を想像してみたらよい。家庭で料理する方がはるかに環境効率がよいはずだし、包装その他の廃棄物も大幅に削減される。食のあり方を再考することは、地球環境に対する最重要の貢献でもあるのだ。
(ハンス・ウルリッヒ・グリム/イェルク・ツィットラウ著、花房恵子訳『ビタミンショックー暴かれた害と効用ー』家の光協会、2003年11月、「監訳者あとがき」)
|
|


