

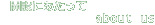
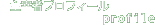

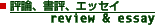

|
 |

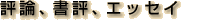
【現代経済学批判ノート】
●「学び合い」と「連帯」の経済学を目指して
経済学は今、グローバリゼーションあるいはグローバル資本主義という奇怪なモンスターの出現にたじろぎ、それがつくり出す危機を捉えきれずに、その権威 は急速に低下するばかりである。経済社会全体の奇怪さ、社会全体に蔓延するモラルハザードを見聞するにつけ、経済学者と自称することに嫌悪感を覚え、もど かしさと焦燥感がにとらわれているのは、はたして私だけであろうか。
社会主義体制の崩壊によって資本主義的市場経済は地球規模に拡大し、人類が育んできたさまざまな経済システムと生活原理がグローバル資本主義の大波に巻 き込まれている。その大波が人類全体に平等な豊かさと安定をもたらすものではないことは理解していても、それに対抗する理念と運動を見いだせずにいる。衝 突と小競り合い程度のものは繰り返されてはいるものの、奔流となって時代をリードする主張は現れない。それどころか、グローバル資本主義の仕組みの解明の 門口にさえ到達し得ていないのではないか。
混迷は、大学の講壇を支配する主流経済学でもある市場原理主義的経済学に止まらず、経済学全般に共通している現象ではないだろうか。多くの経済学者は、 世界経済の総体を俯瞰できる理論的枠組みを模索し、人類の未来への展望について真摯に論議をしなければならない歴史的転換点に直面しているのに、講壇上か ら細分化されたテーマを講じ、過去の議論に依拠した教科書づくりに満足している。少なくとも私にはそのように見える。
講壇経済学が作り出した分析の枠組みの限界が明らかになっているだけではない。貨幣表現された市場経済の地球大的な拡大が、それぞれの民族や地域の文化 的基礎の相違との間に深刻な対立や相克を生み出している現実を座視することはできない。アラブ世界やサハラ以南アフリカの経済の現実、中国をはじめとする いわゆるBRICs(1)の登場の衝撃を観察するならば、そのことを理解することにさほどの時間を要しない。経済学は、講壇派であろうとマルクス派であろ うと、あるいは社会民主主義派であろうと、地球的視野で全体像を見通せる視角を欠いていることは明らかだ。経済学は地球全体を説明する原理ではなくなっり つつあるのだ(2)。
それだけに止まらない。焦眉の人類的課題である地球環境問題を考えてみよう。地球環境危機の最大の原因の一つが人間の工業的経済活動、市場化された経済 活動にあることは明らかであり、温暖化ガスの急増が深刻な景気変動をもたらしていることが共通の認識になっているのに、経済学はそれに対する有効な対応策 さえ出せずにいる。続発する自然災害に直面して、近代世界が作り上げたシステムもハードウェアもあまりに硬直的で、リスクに柔軟に対応できないことが明ら かになっているのに、経済学はこれも「外部不経済」としてしか理解しない。経済学は市場メカニズムをエコロジー的危機を認識できるものに作り替えていく緊 急の課題に直面している。経済学は国民経済の枠を超えて、国益の枠を超えて、地球的視野で問題を提起できる基準の獲得を迫られている。
危機が深まる中で「連帯」や「共生」の理念と市場の整合性に疑念を抱く論者も増えてはいる。しかし、グローバル化した市場を「連帯」の視点から批判しよ うという論議はいっこうに深まらない。「セイフティネット」を張ればよいという。所得格差の地球規模での拡大、絶対的貧困階層の増大に有効に対応できる有 効なネットなどあろう筈がない。システムを変えることこそが求められているのに、なにをどこから始めたらよいのかわからずに、門口で迷い続けている。
そもそも「経済」とは何だろうか。それが確定されなければ、経済学の課題も明らかにならない。これまで経済学者はこれを自明のことと考えてきた。経済と は貨幣表現される市場的関係の総体であると、少なくとも私はこれまでそう考えてきた。貨幣表現される市場経済を自明のもとし、その外にあるものは未開の非 文明的関係で。それは経済学の対象とはなり得ない。いわば経済人類学の対象と捉えられたのである。
現代世界を観察すると、GDPでも貿易額でもよい、とにかくそのような基準で測定すると、貨幣で表現される市場の90パーセントは先進国によって占めら れる。このことから、世界経済とは先進国と先進国間の関係だという通俗的理解が生まれる。世界人口の圧倒的部分を占めるのに、全世界GDPわずかを占めて いるにすぎない非先進世界は経済学の対象とはなり得ないのである。せいぜいのところ、先進国型開発を受容する部分に限って、開発経済学の対象とされたにす ぎなかった。「発展途上」というコンセプトは、このようなものとして確定されたのである。世界人口の圧倒的部分を占める人びとは経済学の対象から切り捨て られたのである。
経済活動を円滑に維持すること、それは人類の歴史と共に古い課題であった。古代王権の最重要政策は、貨幣制度と度量衡制度を統一し、そして交易路の整備 によって交易や通商を発展させること、統一した租税徴収制度を確立することであった。古代メソポタミア、バビロンの王ハンムラビ(在位、紀元前1792- 1750)の命によって制定された法典、いわゆる「ハンムラビ法典」などはその好例である。そこでは所有権、契約その他の保護についての条文が重要な位置 を占めている(3)。
記述された経済学は古代以来、アリストテレスの政治学、経済学、倫理学の体系的記述に始まって(4)、ヨーロッパの学の体系の中心にあった。それはアジ ア世界やイスラム世界についても言えることであろう。世界宗教の登場によって、経済活動を宗教倫理とどのように合致させるかは支配者の重要な課題であっ た。さまざまなすり合わせの苦闘が展開されたのである。市場こそが経済とする「経済」の世俗的理解が普及したのはごく最近のことであり、人類の経済認識の 長い歴史からみると、時間的に見てきわめて短いもので、限定なものと言わざるをえない。
しかもその世俗的認識さえもが、日々現実によって乗りこえられている。国際通貨投機や原油市場投機が常態化している。それを押しとどめる施策などもはや ありはしないのである。
「経済」とは何か、人類の知的先達が解明しようとした「経済」とは何かと問われれば、私は躊躇なく「共に豊かになる」仕組みであると答えたい。一握りの 人びとが豊かになるのではなく、「共に」豊かになることが肝心なのだ。この場合、非効率を実質上是認するような社会主義、共産主義を主張しているのではな い。他者との関係を見据えた豊かさである。地球環境問題を考えてみたらよい。世界の資源のほとんどは先進国によって占有され、消費されている。このままい けば、将来は他の国々には何も残されない。「持続可能な発展」はどのような場合でも前提されるべき規範的枠組みである。
地球上には実に多くの、多様な経済がある。人権が尊重されるべきものあるなら、それらの経済の存在も同じように尊重されなければならないのではないか。 非常に単純なことだが、地球大という視点で考えるときに前提とされるべき枠組みなのである。経済学はそのように豊かになるシステムを解明し、批判し、啓蒙 することものでなければならない。地球大的に共通する経済原理、優勝劣敗ではなく「共に豊かになる」原理を明らかにすることが求められているのではないか。
経済学の父として畏敬されるA・スミスが『諸国民の富』の刊行に先立って1759年に著した『道徳感情論』で、彼はその論述を「同感」 (sympathy)の解明から始めている。その冒頭の記述は感動的である。そこには経済学の最も重要な理念的出発点が示されていると私は考えるので、引 用しておこう。
「人間がどんなに利己的なものと想定されうるにしても、あきらかにかれの本性のなかには、いくつかの原理があって、それらは、かれに他のひとびとの運不運 に関心をもたせ、かれらの幸福を、それを見るという快楽のほかはなにも、かれはそれからひきださないのに、かれにとって必要なものとするのである。この種 類に属するのは、哀れみまたは同情であって、それはわれわれが他の人びとの悲惨を見たり、たいへんいきいきと心にえがかせられたりするときに、それにたい して感じる情動である。われわれがしばしば、他の人びとの悲しみから、悲しみをひきだすということは、それを証明するのになにも例をあげる必要がないほ ど、明白である。すなわち、この感情は、人間本性の他のすべての本源的情念と同様に、けっして有徳で人道的な人にかぎられているのではなく、ただそういう 人びとは、おそらく、もっともするどい感受性をもって、それを感じるであろう。最大の悪人、社会の諸法のもっとも無情な侵犯者さえも、まったくそれをもた ないことはない。」(5)
人間をどのように利己的なものと想定しようと、有徳、不徳にかかわらず、人間には内在的に相手の状況に同感する感情があると、スミスは主張する。「利己 的」という規範が市場経済の主役である経済人の規範と理解されるのが一般的であるが、私はむしろ「同感」こそ人間存在の根源にかかわる共通の経済規範と理 解したいと思う。スミスにとって市場経済研究は人間関係を律する社会的規範の解明であった。彼が言う個人の「利己主義」は、あるいは『諸国民の富』で明ら かにした市場経済の原理は、人間としての連帯性を基盤にしたものであったのではないか。スミスを論じることからはじめたのは、「共に豊かになる」という私 の主張と共通の基盤に立っていると考えたからである。
スミスの原理は、自由放任主義とされ、個人の利己心に経済をゆだねれば、見えざる手によって効率的、合理的解決が図られると理解されてきた。利己心には 類的共感と共存しているなど、相手を打ち負かす競争で相手を哀れむなど、経済学者は考えだにしなかった。その後の経済学はスミスの態度を「道徳哲学」だと して体系外に捨て去り、ひたすら経済学の純化を目指したのである。経済学の文献からは、「同感」も「連帯」も消えてしまった。それらのコンセプトは、市場 経済から疎外された集団のイデオロギーとして生き残ったにすぎなかった。
スミスのこの主張に依拠して見た場合、グローバリゼーションの時代に経済学に求められえいるものは何か。経済学は社会進歩を見通す歴史的予見性についての 権威を取り戻す以前に、その枠組みがもはや「共に豊かになる」、共感するという類的連帯性と無縁のものになっていることを自覚しなければならない。
注
(1)ブラジル(Brasil)、ロシア(Russia)、インド(India)、中国(China)の頭文字をとった造語。2003年にアメリカのゴー ルドマン・サックス社が初めて使用した。この国家群の世界経済への登場の歴史的意義については別の機会に触れたい。
(2)紀伊国屋書店のPR誌『アイ・フィール(i feel)』2004年第30号(秋号)に「主流派経済学にカウンターパンチを」と題する、中谷巌と岩井克人との対談を発見した。岩井の評価はさておき、 中谷はカウンターパンチの対象である主流派経済学の旗手の一人と私は考えてきたが、その旗手が自らにカウンターパンチを加えるというのだから、奇妙な話で はないか。彼によると、西洋起源の経済学を西洋の一神教的理念と密接な関係がある。「古典派・新古典派経済学はその延長線上にある。だから・・・きわめて 抽象的かつ形而上学的な観念の世界から生まれてきたということができる。そういうことは、われわれ日本人が、経済学を学ぶ際に押さえておかなければならな いポイントです。」(9ページ)多神教と稲作文化いう文化的土壌に接ぎ木された学問であり、違和感があるのだという。そして、「実は私も、日本に合わない 理論を日本に持ってきて、あたかも伝道師のように説いて回るのは、もう止めようと考えるようになりました」と自己批判の弁を披瀝している(8ページ)。こ の自己批判がどの程度のものか、日本の文化的伝統に根ざした市場経済学とは一体どのような内容なのか、彼の今後の議論を見守りたい。一言付け加えさせても らえば、現代西洋経済学を一神教や形而上学的観念と結びつける態度は承服できない。経済学を今のように純化させていった歴史には別の説明が必要である。
(3)中田一郎訳『ハンムラビ「法典」』古代オリエント資料集成1、リトン、2002年5月。
(4)経済や経済学の語源となったオイコノミヤは本来、家庭経済を意味していた。そ文献的出発点はクセノポンにまでさかのぼる。あるいはそれ以前について も多くの断片が存在するのかもしれないが、まとまった著作としては、紀元前369年から354年頃に著された『オイコノミコス』が最初と思われるる。
(5)アダム・スミス著、水田洋訳『道徳感情論』(上)、岩波文庫、2003年2月、24-25ページ。
|
|


